今回は「超入門!スラスラわかるリアルワールドデータで臨床研究第2版」を読んだ感想を書いていこうと思います。
今年の1月に第2版が出ておりますので、購入されるときは誤って初版を選ばないようご注意ください。
書店では起こり得ませんが、ネットで購入するとたまに間違えますよね・・・(自分だけ?)
リアルワールドデータとランダム化比較試験
臨床研究といえば何か。
多くの人がランダム化比較試験(RCT)と答えると思います。
もちろんRCTは臨床研究の王様でありますが、大きな注意点もあります。
それは多額の費用がかかることから簡単には出来ないことや、対象も実際に知りたい集団を組み入れられるとは限らないことなどが挙げられます。
例えば今の医療現場って高齢者ばかりですが、75歳未満の臨床試験の結果をその年代で本当に外挿できるか(あてはめられるか)ってのは分かりません。
このような一般化可能性の低かったり、小規模なイマイチな集団であったりすることを「へなちょこRCT」と表現するのはまさに言い得て妙ですね。
実際にRCTよりも質の高い観察研究はいっぱいあります。
その対抗馬として最有力になっていくのは間違いなくリアルワールドデータ研究だろうと強く感じさせてくれました。
リアルワールドデータの種類
本文では以下に分類しています。
①患者レジストリー
事前に入力内容を指定し、各医療機関に記載してもらうものです。
例えばがん登録やNational Clinical Database(NCD,外科手術レジストリー)などがあります。
自分が関わりが深いものとしては日本ICU患者データベース(Japanese Intensive care Patient Database, JIPAD)もここに該当します。
②保険データベース
医療保険情報などが分かるレセプトを元にしたデータベースが主になります。
例えばNational DataBase of Health Insurance Claims and Health Checkup,レセプトデータ)や民間が提供するJMDCデータ、DeSCデータに加えて、Diagnosis Procedure Combination(DPC)データも含まれます。
まさにこれらが研究で使いやすい花形で、特にDPCデータこそ「リアルワールドデータ研究の代名詞」とも言えると感じます。
問題はそれぞれのデータに得意不得意があるので、これらをきちんと把握して自分の臨床疑問にあった正しいデータを選択することと感じました。
今後の活用と課題
2017年の次世代医療基盤法により、各医療機関の医療情報を収集し研究開発や産業創出を推進することが推奨されました。
そして2023年には改正次世代医療基盤法となり、新たに個人を特定しない加工した情報が作られ、それぞれのデータベースの情報が連結することが目指されるようになっています。
一方で現状でも匿名化はされているにも関わらず、あまりに厳しい運用方針は研究者の敷居を高くしてしまっている側面もありますね。
海外との大きな違いで、いかにも日本の役所って感じです。。。
さて、いかがでしたでしょうか。
現状はまだリアルワールドデータ研究ができる環境は限られていると思います。
ですが、自分の疑問を形にするための宝の山だと感じます。
もちろん扱いの難しいデータもありますが、今後のトレンドになっていくこと間違いなしです。
例えばJIPADについては死亡の扱い方が難しくなってるのかなあとも感じます。
意思決定支援の考え方が進み無益な治療はきちんと中止している施設が増えてきている中では、死亡というアウトカムが悪いとは限らないからです。
いつかこれは研究したいと思っています。
自分も完全には理解できていないので、また勉強しつつ今扱っているDPCデータの解析を頑張ろうと思います。
本日はこの辺で、ではでは。
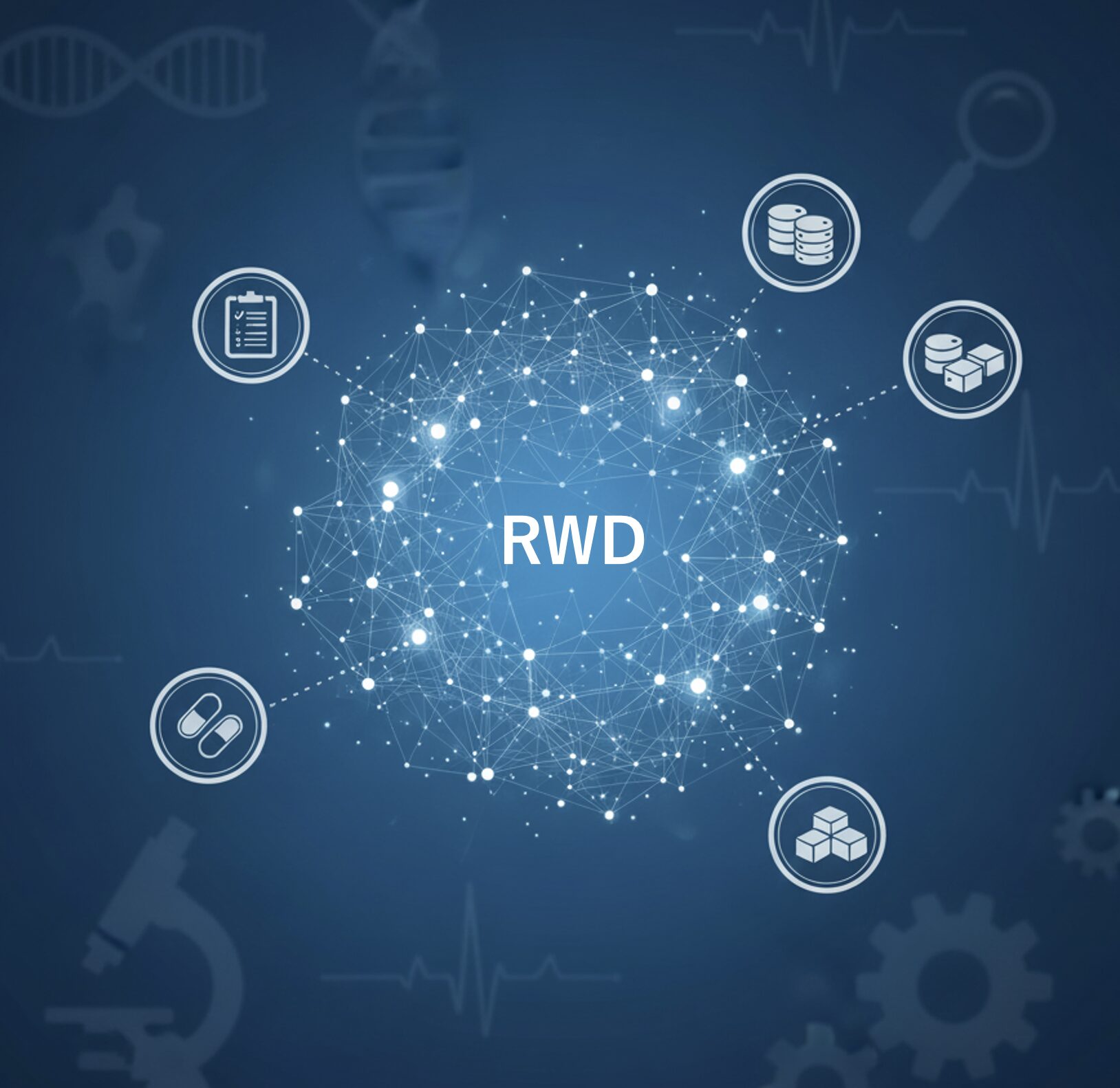


コメント