今回は「できる!臨床研究最短攻略50の鉄則」を読んでの書籍レビューをしていこうと思います。
2017年に初版が出たのでだいぶ古い本ではありますが、素晴らしい一冊です。
なかなか通読ができていなかったので、今回時間をとって読んだ感想を書いていきます。
研究の心構え
「なぜあなたは研究するのか」という問いかけから本書は始まります。
確かに自分の名声のためだったり、出世のためだったり、上司の命令だったり、色んな動機で研究する人を見てきました。
ですが著者の言う通り「患者のアウトカムの改善」以外には有り得ませんね。
当たり前のことですが、絶対に忘れてはいけない内容です。
この研究云々の前の話って、あまり書かれていないので改めて考えさせられました。
またメンターも色々ですから、合わなかった時とか大事ですよね。
自分も過去に酷い目にあい、研究諦めた経験があります。
だが一方でメンターを基本的には立てるという姿勢も忘れてはいけません。
年功序列、とは違いますが、指導者に従うのは研究も臨床も変わりませんね。
デザイン力を磨く
ネタ帳を持ち歩くというのは有名ですね。
自分も常にメモできるようにして、なるべくClinical Questionを逃さないようにしています。
小説家もよく言いますが、いいアイデアはいつも突然降ってきます。
その集めたネタをいかに調理できるか、いかに先行研究を調べてResearch Questionに構造化できるか、というところで研究の大勢は決しているのでしょう。
この辺りは多くの臨床研究本と共通している内容ですが、それだけ重要なことと再認識しますね。
目から鱗だったのは論文を研究プロトコルを書き終えた時点で書き始めるということです!
確かにデータ集めをする直前が、一番先行研究の知識は整理されてますもんね。
なんならMethodsまでは書けちゃいます。
いつも時間が空いて忘れたり、それを言い訳に後回しにしたり、、、そしてそのままお蔵入りへ。。。
これは自分も今取り掛かっているネタから実践していこうと思いました。
疫学の基礎
偶然誤差と系統誤差の話に始まり、各種のバイアスや交絡についてまとまっています。
「サンプルサイズが少ない」って自分も過去によく言われたんですが、それって偶然誤差の問題だけなんですよね。
逆に言えばダメなデータでもサンプルサイズ増やせば、統計学的に差がついてしまうこともあります。
介入研究では不必要なサンプルサイズは侵襲になりますし、きちんと最低限で行うことも基本です。
統計学の基礎
臨床医学の方が統計学より遥かに難しいと言って頂けると、臨床家としては頑張る気になります。
まあ、本当なのかは分かりませんけれども、、、笑
愚直に信じて学ぶのみですね。
ここも基礎とは言いつつも視覚的に非常にハッとさせられる内容が多く、学びが多い項です。
非常にシンプルな解析から多変量回帰分析、傾向スコアマッチング、操作変数法まで、広く浅く書いてくれています。
繰り返し読んで理解を確かにしないといけませんね。
いかがだったでしょうか。
部分的ではありますが、感想を書いてみました。
また本筋からは逸れますが、本編も言わずもがなですがコラムの質も本当に高いです。
読み飛ばすには重すぎる深い内容が、章の合間に散りばめられており手が止まってしまいます。
こういった時代を作ってきた人たちの箴言に簡単に触れられるので、読書って素晴らしいですね。
今月は統計強化月間にしていこうと思っているので、どんどん読書して勉強していこうと思います。
本日はこの辺で、ではでは。

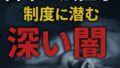

コメント